ご要望に合わせて選べる
基本の葬儀プラン
斎場案内センターがご提案する基本の葬儀プランでは直葬・一日葬から家族葬、そして一般葬まで幅広く対応致します
越谷市エリアの葬儀社
【斎場案内センター】
斎場案内センターは、越谷市エリアにおいてお寺が直接運営している葬儀社です。
当社の理念は、故人様、そしてご家族・ご参列者様みなさまの想いが、
葬儀として一つの形になって行われる事にあります。
現代は様々なスタイルの葬儀が執り行われております。
多種多様なニーズに対応しつつも、伝統として守るべき形を残し、
参列者皆様の心に残り続けるような葬儀になるようサポートいたします。
越谷市周辺のお葬式なら
お任せ下さい
 斎場案内センターでは、宗教・宗派・宗旨を問わず、
斎場案内センターでは、宗教・宗派・宗旨を問わず、お葬式をお考えのすべての皆さまがご利用いただけるセレモニーホール『光輪法殿』にて
家族葬・一日葬・直葬とお客様のご希望の葬儀を執り行うことができます。
通夜から葬儀・葬式にかけての一連の儀式は親愛なるご家族に
最期の別れを告げる場でございます。
それと同時に、故人様の最期の言葉、無言の想いに耳を傾け、残された
ご家族・ご遺族の皆様自身の生き方、死に方を学ばせて頂く機縁となります。
越谷市有数の
充実した葬儀設備
斎場案内センター直営のセレモニーホール『光輪法殿』では、式場・お清め所・宿泊可能な控室・冷蔵設備を完備した御遺体安置室と充実の設備を完備しております。埼玉という地域性を考えて70台駐車可能な大型の駐車場をご用意しております。
またお寺、霊園が併設しているので、葬儀後の年忌法要やその後会食、お墓参りといったすべてを同敷地内で執り行えるように設備しております。
葬儀を行う事は人生に何度も経験がある事ではありません。当社では緊急の事でお困りの際や、事前準備として葬儀全般の事を調べたい方などのご相談もお受けしております。
どうそお気軽にお電話または直接お越しいただいて、ご相談をお受けいたします。
 光輪法殿外観
光輪法殿外観 安置所
安置所 エントランスホール
エントランスホール 菩提(式場)
菩提(式場) 沙羅(お清め所)
沙羅(お清め所) 応接室
応接室 女性用トイレ
女性用トイレ 多目的トイレ
多目的トイレ実は仏教ではないさまざまな葬儀の習慣
死者のことを刑事用語で

刑事ドラマなどで「ホトケ」や「マルタイ」「ニンチャク」などという変わった言葉を聞くことがあります。これは刑事用語でそれぞれ「亡くなった人」「対象人物」「人相や着ているもの」などの言葉を略したり、伏せたりして表現しています。一般的な用語でも死人という意味として仏という言葉は使われることがあります。もともとの意味としては、その文字の通り仏教の開祖である釈迦を指す言葉でした。また語源をたどるならば悟りを開いた人という意味もあります。では、なぜ亡くなった人のことを仏と呼ぶようになったのでしょうか。
「祓う」という発想の神道

実は日本人の死者に対する考え方というのは非常に面白いものがあります。亡くなった人のことを「ホトケ」と呼んで悟りを開いた人だと呼ぶのにも関わらず、葬儀が終わって家に帰るときには塩をまくのです。塩には悪しきものを払うという意味合いが込められています。相撲などで取り組みの前に塩をまくのもそのためです。また招かざる客が来たあとに塩をまくのもその例でしょう。このような祓うという発想は実は仏教から来ているのではなく神道から来ているものです。神道の基本発想は、悪しきものを遠ざけ祓うというところからきています。神社でお祓いなどをするのもそのためです。塩は腐敗を防ぎます。そのため、塩には悪しきものを遠ざける効果があると考えられたのです。
神道では亡くなった人間は荒御霊として荒ぶる精霊になると考えていました。そのため、そうした邪なるものを祓うために塩をまいたのです。一方仏教では、宗派によって考え方は異なりますが、亡くなった人間は最終的に仏となって悟りを開き極楽浄土に辿り着くという風に考えられています。そのため、亡くなった人間は悪しきものではないと考えているのです。
現在のわたしたちの葬儀の習慣の起源とは

葬儀における習慣の中で、死者が帰ってこないようにする意味合いを持つものはたいてい神道由来のものです。また、ものによっては土着信仰のものであったり、方違え(かたたがえ)や友引などは陰陽道を由来としています。葬儀における習慣というのは必ずしも仏教由来ではないのです。北枕や火葬は仏教から(北枕に関しては諸説ある)、振り塩は神道から、友引は陰陽道から、と今の日本の葬儀の習慣はさまざまなところから来ているのです。
お寺が行うさまざまな種類の葬儀

「お寺の家族葬」は宗教法人善源寺光輪事業部の提供する家族葬サービスの名称です。葬儀の習慣がさまざまなものを由来としているように、葬儀は仏教だけのものではありません。本事業部では宗旨、宗派などを問わず葬儀を行うことができます。通常の仏教式の一般葬のほか、家族葬や無宗教葬などさまざまな葬儀の方式をお選びいただくことができます。埼玉県松伏町周辺、越谷、春日部、吉川などの地域で葬儀の際は、光輪事業部にご相談ください。

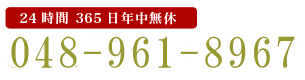

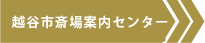
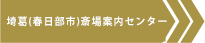








 地図を開く
地図を開く