ご要望に合わせて選べる
基本の葬儀プラン
斎場案内センターがご提案する基本の葬儀プランでは直葬・一日葬から家族葬、そして一般葬まで幅広く対応致します
越谷市エリアの葬儀社
【斎場案内センター】
斎場案内センターは、越谷市エリアにおいてお寺が直接運営している葬儀社です。
当社の理念は、故人様、そしてご家族・ご参列者様みなさまの想いが、
葬儀として一つの形になって行われる事にあります。
現代は様々なスタイルの葬儀が執り行われております。
多種多様なニーズに対応しつつも、伝統として守るべき形を残し、
参列者皆様の心に残り続けるような葬儀になるようサポートいたします。
越谷市周辺のお葬式なら
お任せ下さい
 斎場案内センターでは、宗教・宗派・宗旨を問わず、
斎場案内センターでは、宗教・宗派・宗旨を問わず、お葬式をお考えのすべての皆さまがご利用いただけるセレモニーホール『光輪法殿』にて
家族葬・一日葬・直葬とお客様のご希望の葬儀を執り行うことができます。
通夜から葬儀・葬式にかけての一連の儀式は親愛なるご家族に
最期の別れを告げる場でございます。
それと同時に、故人様の最期の言葉、無言の想いに耳を傾け、残された
ご家族・ご遺族の皆様自身の生き方、死に方を学ばせて頂く機縁となります。
越谷市有数の
充実した葬儀設備
斎場案内センター直営のセレモニーホール『光輪法殿』では、式場・お清め所・宿泊可能な控室・冷蔵設備を完備した御遺体安置室と充実の設備を完備しております。埼玉という地域性を考えて70台駐車可能な大型の駐車場をご用意しております。
またお寺、霊園が併設しているので、葬儀後の年忌法要やその後会食、お墓参りといったすべてを同敷地内で執り行えるように設備しております。
葬儀を行う事は人生に何度も経験がある事ではありません。当社では緊急の事でお困りの際や、事前準備として葬儀全般の事を調べたい方などのご相談もお受けしております。
どうそお気軽にお電話または直接お越しいただいて、ご相談をお受けいたします。
 光輪法殿外観
光輪法殿外観 安置所
安置所 エントランスホール
エントランスホール 菩提(式場)
菩提(式場) 沙羅(お清め所)
沙羅(お清め所) 応接室
応接室 女性用トイレ
女性用トイレ 多目的トイレ
多目的トイレ春日部での葬儀やお通夜に際して覚えておきたいマナー
まずはお通夜にお伺いする

お通夜というものは、本来ご遺族様やご親族様といった、近親者の方々によって執り行われる、今生のお別れ式です。
そのため、ご親族様や近親者の方ではないという方々は、お通夜は遠慮していただき、その翌日に執り行われる葬儀にお伺いする、のが礼儀作法でした。
というのも、故人様はまだお棺に入らず一晩布団に寝かされている状態で、そこで対面などのお別れが行われたからです。
しかし近年ではお通夜に祭壇を本格的に飾り付ける、という手法をとられるお家も多く、お通夜と告別式の区別が薄まってまいりました。
そのため、上司や部下、同僚の方といったお仕事の関係者の皆様やご友人など、告別式に参列することができない時には、お通夜の席に参列される、ということも一般的になってまいりました。
お知り合いの訃報に接したら、まずはお通夜にお訪ねいただくというのが、現代のマナーと考えてもいいでしょう。
葬儀にも参列できないとき

葬儀を執り行う地域から遠く離れていてお通夜に参列できないという時や、あまりにも突然のことのため、準備などが整わずお通夜に参列することができない、といった場合には、弔電で哀悼の意をお伝えするようにしましょう。
やむを得ない事情で葬儀にも参列することができない際には、香典にお悔やみの手紙を添えて郵送されたりしても良いでしょう。
たとえば、「このたびは何々様ご逝去との由、心からお悔やみ申し上げます」と始めて、中ほどに心からの慰めの言葉を書き記し、文末には「同封のもの誠に些少ですがご霊前にお供えくださいますようにお願い致します」と書いて文を締めていただきます。
この時には必ず香典袋に現金を入れ、現金書留で送ることがマナーです。
葬儀が執り行われる前に会場へ

葬儀と告別式というものは、連続して行われることが多いので同じものと思われる方もいらっしゃいますが、実のところその意味合いは異なります。
葬儀は、故人様が成仏して下さるのをお祈りする儀式で、ご遺族様をはじめ近親者の方が集まって行われるものです。
そのため、ご友人や会社の同僚の方などは告別式からご参列いただくのが一般的です。
近年は一緒に葬儀と告別式が行われますので、葬儀が執り行われる20分前ぐらいに会場に到着しておかれるのがマナーです。
前日のお通夜に参列し、香典をお渡し済みであれば葬儀の席で改めてお渡しいただく必要はございません。
受付にはお名刺を差し出していただいたり、ご記帳をしていただくだけで結構です。
喪章は喪服の代わりにはなりません

時折ですが、一般の弔問客の方が平服に喪章をつけて、それを喪服として葬儀に参列しているという姿をお見かけすることがあります。
この方法は、実は大きな間違いであり、絶対に避けなければならない行動です。
喪章は、ご遺族様やご親族の皆様、そして世話役の方など、喪家側の人間として喪に服している、ということを示すためのサインです。
そのため、喪章をつけた平服は、当然のことながら喪服の代わりは務まりません。
また、そのような事情がありますので、ご遺族様以外は喪章を付ける必要もありません。
このように葬儀に関しては様々なマナーや決まりごとがございます。
春日部を始め、埼玉東部地域での葬儀を承っております「お寺の葬儀屋さん」では、こういった葬儀のマナーについてのご案内も行っております。
どうぞお気軽にご相談下さいませ。

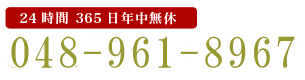

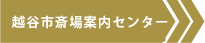
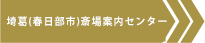








 地図を開く
地図を開く